「この町が大好き」と言える大人になってほしい。大町拠点が取り入れる自然体験。

地域の子ども達のもう一つの家を目指す、第三の居場所。今回ご紹介するのは、長野県は大町市にある拠点です。ここでは、子ども達の体験格差を解消することを目的に、B&G海洋センターの施設を活用したアクティビティを取り入れて年間プログラムを作っています。
立山黒部アルペンルートの玄関口
大町市は、長野県北西部に位置。長野市と松本市からそれぞれ約1時間のところにある人口2.8万人ほどの町です。立山黒部アルペンルートの長野県側の玄関口としても知られ、全国各地から観光客が訪れる場所でもあります。
市内には、標高3,000m級の山々が連なる北アルプスと「仁科三湖」と呼ばれる木崎湖・青木湖・中綱湖の3つの湖があり、自然を肌で感じられるアクティビティが盛ん!夏は釣りやSUP、湖畔キャンプ、冬はスキーで賑わいます。
大町でしかできなことを体験してほしい
恵まれた豊かな自然を、大町で生きる子ども達にも思う存分体験してもらいたいと話すのは、第三の居場所を運営する特定非営利活動法人キッズウィルの甘利直也さんです。

甘利さんは、大町生まれ・大町育ち。多くの友人達が、卒業後、東京をはじめとする都市部へ出ていく中で、地元で生きることを選択しました。
「自然豊かな大町が好き。拠点に通う子ども達が大人になった時、生まれ育ったところにはいっぱい楽しいものがあるんだと思い出してもらえるような体験をしてほしいんです」

そうした甘利さんの考えから、大町拠点ではアクティビティを取り入れた年間プログラムを組んでいます。
春には釣り体験、夏にはカヌー体験やBBQ、秋にはサツマイモ堀りなどの農業体験、冬には雪遊びと、大町の自然だからこそ楽しめる四季折々の体験学習を用意しています。
また、北アルプスの雪解け水に恵まれた大町市は、食が充実。野菜や山菜、そばなどを使った調理教室も実施。食育にも積極的です。
「自然体験は、子ども達にとって恐怖もありますが刺激になります。活動中はとても生き生きした表情を見ることができますし、活動後はひとまわり大人になった感じがするんです」
夏の目玉行事、合同カヌー体験教室に密着

そんな自然体験の様子を一目見ようと、8月上旬に木崎湖で開催されたB&G海洋センターでのカヌー体験教室を訪れました。大町拠点を利用している子どもと地域の子どもたが一緒になった合同教室の参加者は、小学3年生から中学生まで約20名。2時間ほどのプログラムで、一人ずつカヌーに乗り湖を駆け回ります。

初めは、非日常の空間に緊張しているう様子の子ども達でしたが、だんだん友達とじゃれあったり、おしゃべりをしたりするように。カヌーに乗り込む頃には、すっかり場に馴染み、積極的な姿勢が見られました。


たっぷりカヌーを楽しみんだ後、ラストは記念撮影です。
やり切った子ども達の表情が印象的。2時間という短い時間の中でも、子ども達は自信をつけたように感じられました。

いざという時、思い出してもらえる場所に
大町拠点が開所して1年。そばで子ども達を見守り続けてきた甘利さんは、「拠点に通い出してから、子ども達の表情は明るくなった」と振り返ります。

「拠点に通う子ども達のなかには、家庭環境に困難を抱えている子どももいます。おうちの方の養育能力が乏しい家庭。ひとり親でお父さんまたはお母さんどちらかの愛情をもらえていない子ども。親が子どもに関心を示さず家でゲームばかりしている子ども。様々です」
家庭が安心できる場所ではない。大人に頼れない。子どもたちは、拠点に通い出したばかりの頃、寂しさから大人に甘えることが多かったそう。しかし、拠点で生活を共にする中で、生活リズムが整い、学習にも意欲的に取り組むなど主体性を持ち始めています。
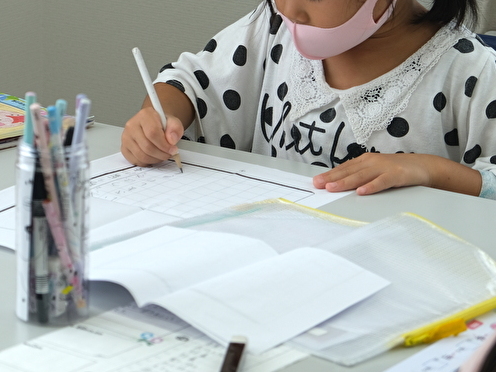
「大人になったら都会へ出ていく子どももいるでしょう。もし彼らが何かしら挫折して地元に戻りたいと考えた時、きっとおうちに帰るのは難しい。緊急事態の時に避難できる場所、いざって時に頭の中に出てくる場所であれるよう、拠点は子ども達にとって安心できる環境でありつづけたいです」
子ども達が大人になる10年、20年先も考えて拠点を運営する甘利さん。今後も、大町だからこそできる自然体験プログラムを取り入れながら、「このまちが好き」と言える心を育んでいきます。
取材:北川 由依

日本財団は、「生きにくさ」を抱える子どもたちに対しての支援活動を、「日本財団子どもサポートプロジェクト」として一元的に取り組んでいます。





