故人の想いと子どもたちの未来がつながる。「遺贈寄付」で箕面第二拠点が開設

困難な状況にある子どもたちのための施設「子ども第三の居場所」。2021年10月、大阪府箕面市に、市内で2つ目の拠点がオープンしました。
実はこの箕面第二拠点を開設した費用の一部は、生前に「未来の子どもたちのために」と遺言を残された水野久榮さんの「遺贈」によるものです。
時を越え、水野さんの想いは子どもたちへ届いたのでしょうか。子ども第三の居場所の箕面第二拠点の山本将さんと森由佳梨さんからメッセージをいただきました。
最寄り駅から歩いてすぐの場所。コンクリート造りのスマートな印象の建物が箕面第二拠点です。
金属製のぴかぴかした階段を上がり2階に到着すると、子どもたちが食事をするための大きなダイニングテーブルとキッチン。

3階には、開放的な空間の中にこたつが2つ。ここで子どもたちが宿題をしたり、ゲームをしたり、おしゃべりをして楽しむ姿が目に浮かびます。


どの空間も洗練されつつも遊び心があり、温かみを感じられる印象。
出迎えてくれたのは、箕面第二拠点のマネージャーの山本将さんとチーフの森由佳梨さんです。

「子ども達の居場所があることだけでも大変ありがたいのですが、この建物を見たら、子どもたちも『行ってみたい』『通いたい』と目を輝かせてくれそう。本当にとてもありがたいことです」(山本さん)
すでに箕面市には子ども第三の居場所が1カ所ありました。今回新しく開設されたのは2カ所目。
しかし、箕面市の困難な状況にあるすべての子どもに──と考えると、「まだまだ施設の数は足りていない」と山本さんは語ります。

「学童保育のように1つの校区に1カ所はあるのが理想です。でもそれはあまり現実的ではありません。それでも3つから4つの校区につき1カ所は、困難な状況にいる子どもたちをケアする施設が必要だと考えています」
箕面市は大阪府民からは生活に余裕がある方が多いと知られるエリア。しかし、すべての子どもたちが裕福な家庭で育っているわけでもなければ、経済的な事情以外にもさまざまな困難があります。
そんな子どもたちが学校の放課後に気軽に立ち寄れる場所。宿題をする習慣をつけたり、思い切り遊んだり、きちんと栄養のある食事を摂ったりできる場所。
子ども第三の居場所 箕面拠点は、子どもたちのセーフティネットとして、欠かすことのできない場所になっています。
「子どもたちの未来のために」遺贈とは?
皆さんから日本財団に寄せていただいた寄付によって運営している子ども第三の居場所。なかでも、この箕面第二拠点の開設費用の一部は「遺贈」による寄付が充てられています。

遺贈とは、自らの財産を特定の個人や団体に遺すことです。遺言書を作成することで、生前に自分が築いた財産を未来に託すことができます。
箕面第二拠点の費用の贈り主は水野久榮さん。生前に「子どもの支援のために使って欲しい」という遺言と共に財産を遺されました。
水野さんの没後、日本財団が託された財産の用途を弁護士と話し合った末、子ども第三の居場所事業に利用させていただくことになったのです。
東日本大震災以降、日本に寄付文化が定着してきたために、遺贈件数は増加傾向になります。国税庁発表の最新のデータによれば、2019年の遺贈件数は780件、金額にして167.6億円です。
日本財団遺贈サポートセンターでも、2019年には遺贈件数5件、金額で約4.3億円をお預かりしました。
遺贈のご相談にいらっしゃる方の寄付先のご希望はさまざまです。特定の団体を指定される方もいらっしゃれば、社会の役に立つように使って欲しいというような希望の仕方をする方もいらっしゃいます。
そんな寄付先に関するご希望の中でも最も多いのは、「子どものために使って欲しい」というもの。「自分は子宝に恵まれなかったから」「戦時に子どもを亡くしたから」「自分がお金がなくて大学に通えなかったから」。想いはさまざまですが、自分の築いた財産を子ども支援という形で未来の社会につなげたいと考える方が多いのです。
遺贈で受け継がれる子どもたちへの想い
そして今、そんないくつかの「未来ある子どものために」という想いの内の1つが、子ども第三の居場所という形になったのです。時を越えて受け継がれた想い。子どもたちに届くのでしょうか。
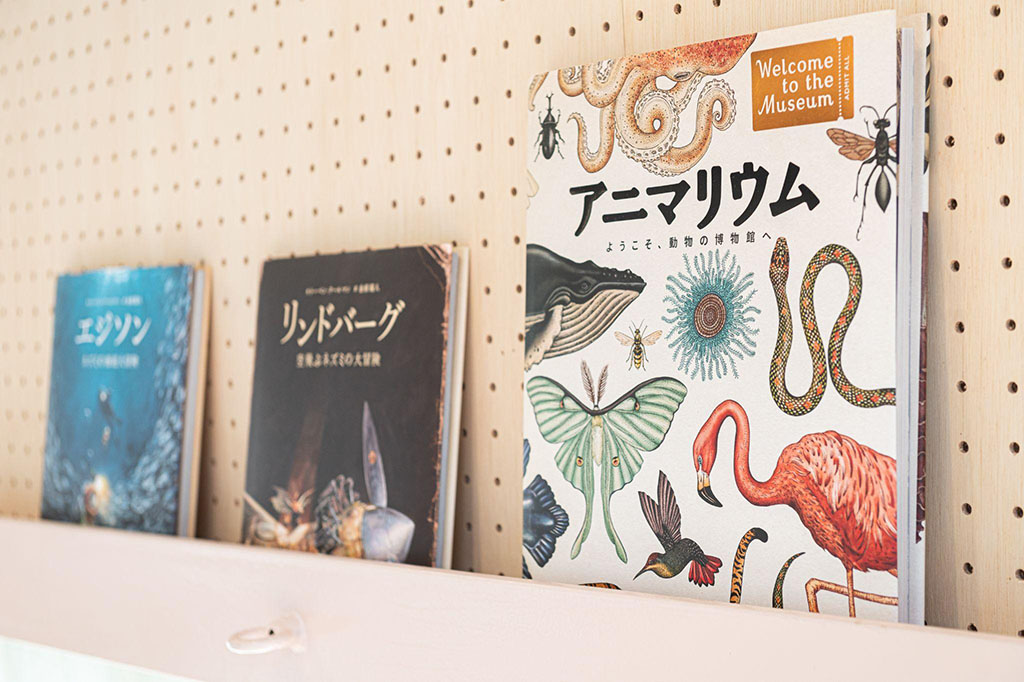
「箕面の子ども第三の居場所では大きく2つの方針を定めています。1つは、ほっと一息つける場所にする。いろんな家庭環境の子どもたちがいるので、ここではいつも自然体でいられるような居場所にしたいですね。
もう1つは生き抜く力を育むことです。仲間と協力したり、最後までやり抜く根気だったり。そういった力をこの場所で身につけてもらいたいと思います」(山本さん)
チーフの森さんが、箕面第一拠点でのエピソードを話してくれました。

「子どもがやりたいことを経済的な理由でチャレンジさせてあげられない、というご家庭もあります。
ピアノをやりたいという小学生の女の子がいました。ピアノは高額なので最初はあきらめていたのですが、施設で一緒にピアノの練習をできるようにしたんです。3カ月くらい、こっそり練習をして、サプライズでお母さんに披露したら、すごく喜んでもらえて。
その子が中学校に進学してから、ピアノで学年1番になったそうなんです。1番になる経験は、自信になるし、次に何かを挑戦しようという原動力にもつながります。
そういう未来につながる種みたいなものを、いっぱい植えてあげて、挑戦したいとかやり遂げたいって気持ちを育めたら、と思います」(森さん)
まだ開設したばかりの箕面第二拠点。これからやってくる子どもたちも、いろいろな経験を通じて、未来を切り拓く力を養っていってくれることでしょう。
第三の居場所を通じてつながる、故人の想いと子どもたちの未来。遺贈が紡いだご縁について、山本さんは次のように語ります。

「遺贈について子どもたちにも伝えていきたいと思っています。
大変なこと、嫌なこともあるけれど、見ず知らずの人の中にも、自分たちを応援してくれている人がいるということ。みんなには、いっぱい味方がいるんだよと、知ってもらいたいです。
そして、子どもたちが大人になったときに、この恩を次の世代に返していく。託していただいたバトンを、子どもたちが未来に繋げていく。そのような素晴らしい機会をいただけたと感じています」(山本さん)

日本財団は、「生きにくさ」を抱える子どもたちに対しての支援活動を、「日本財団子どもサポートプロジェクト」として一元的に取り組んでいます。





