社会のために何ができる?が見つかるメディア
企業がNPOとタッグを組むことが、多様な社会課題を解決する鍵に。NPOとの連携を助けるサステナNetに聞いた
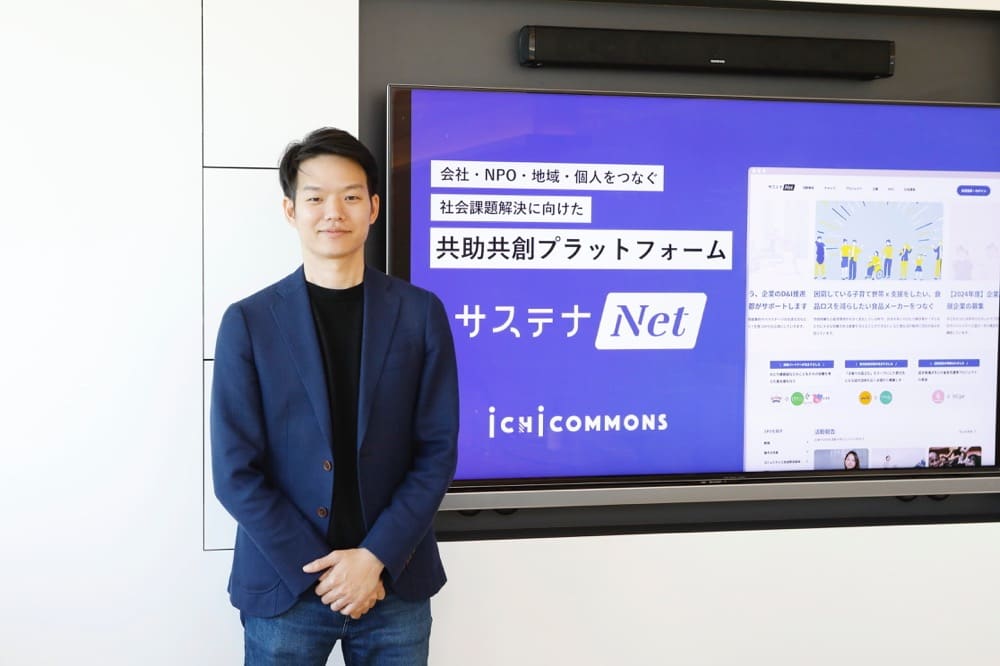
- 企業とNPOの連携が進まないのは、社会課題やNPOの団体の存在が知られていないことが大きな要因
- 「サステナNet」は、さまざまな社会課題やそれに取り組む団体の活動を可視化したプラットフォーム
- 企業とNPOが連携することで、社会課題解決に向けて多角的なアプローチができる
取材:日本財団ジャーナル編集部
近年、企業に社会課題解決を求める空気ができつつある一方で、社会課題に深い知識のあるNPOと企業の連携率はわずか8パーセントに過ぎないという。連携率を上げるには、企業とNPO、双方にとってメリットがあることや、それぞれの強みを理解し、どのような社会的価値が得られるかなどを可視化することが必要だ。
「誰もが社会課題解決の主役になれる世界」をビジョンに掲げるICHI COMMONS(イチ・コモンズ)株式会社(外部リンク)では、NPOや社会的事業者・企業・個人が、社会課題解決の仲間と会えるプラットフォーム「サステナNet」(外部リンク)の運営を行っている。
今回は、同社代表取締役の伏見崇宏(ふしみ・たかひろ)さんに、サステナNetを通して実現できることや、企業とNPOが連携するメリット、連携率が低い現状の背景などについて聞いた。
「何から始めたらいいか分からない」という声から生まれたプラットフォーム
――ICHI COMMONSについて教えてください。
伏見さん(以下、敬称略):ICHI COMMONSは2020年1月31日に登記したスタートアップ企業です。前職では、社会的インパクト投資という、社会課題の解決に取り組む方々に投融資を行う仕組みづくりに携わっていました。
さまざまな企業や投資家、NPOの方々と出会い、コミュニケーションをする中で感じたのが、多様な社会課題の存在や、その解決のために活動する人たちの存在が知られていないことです。
まずはこの大きな課題を解決するために、社会課題の解決を軸に置き、相互理解を育むためのインフラを作りたいという思いから創業しました。

――サステナNetとはどんなサービスでしょうか。
伏見:2021年にスタートした事業で、社会課題解決に取り組みたい団体や個人が学び、つながることができる、共助共創のプラットフォームです。

伏見:サステナNetでは「教育」や「働き方改革」、「自然環境と生態系」など、12のテーマに分け、全54の社会課題を提示しています。また、それぞれの課題のページでは、背景や関わるステークホルダー、解決策に加えて、その課題に取り組むNPOを紹介しています。
企業側は、自社が解決したい課題のページを見るだけで、現在登録していただいている約500の団体の中から、連携し得るパートナーが探せるという仕組みです。
![社会課題
いま、どのような社会課題があるのかをまとめました
[教育]
・教育機会の地域格差
・生涯学習・リカレント教育
・学術研究環境
・教育現場の疲弊
・専門知識の社会実装
・多様な学びの機会の拡充
[働き方改革]
・働き方改革とワークライフバランス
・非正规雇用
・AIなどの台頭による雇用喪失
・生産年齢人口の減少
・リスキリング](/wp-content/uploads/2025/03/ichicommons00007.jpg)
――そもそも、なぜ企業とNPOの連携率が低いのでしょうか。
伏見:これは推察ですが、歴史的に企業とNPOが対話する機会がなかったのが大きな理由ではないでしょうか。
社会貢献の位置づけはさまざまですが、企業にとって、NPOとは「社会貢献の一環で寄付をする対象」という捉え方が一般的だったのではないでしょうか。寄付をすることで社会課題について学んだり、自社にとって新しい機会を見つけ出したりするということに結びつけることができていなかったのです。
また、NPO側には「自分たちの活動が企業に対してどんな価値を与えることができるか?」という視点が不足していたのではないでしょうか。
そのため、多くの企業は、サステナビリティを推進したい、そのためにNPOと連携したいという意欲がある一方で、「何から始めたらいいか分からない」「信用できる団体が分からない」「どこの団体で何ができるかが分からない」という課題を抱えているのではないかと思います。
ここで生じていた分断を乗り越え、企業もNPOも、ともに社会的インパクトを生み出す「パートナー」としてマッチングすることを目的としたサービスが「サステナNet」です。いわばお見合いの場ですね。これまでのマッチング成立数は50を超えています。
企業とNPOが連携しなければ生まれなかった、ユニークなアイデアの数々
――企業はどのようにサステナNetを活用しているのでしょうか。
伏見:まず、ご登録いただいた団体には、必ず1時間程度オンラインでインタビューを行い、活動内容をまとめた紹介動画を作成しています。
サステナNet内には「わくわく寄付コンペ」(外部リンク)と題して、企業がこの動画をもとにさまざまな課題について学び、現場で活動される方の声を聞いた上で、協力団体を募集し、応募団体の中から企業の従業員が投票で選ぶプロジェクトページを作りました。
単に寄付するだけにとどまらず、コンペ終了後には選ばれた団体と企業との対話の場を設け、新規事業開発や地域連携、社会課題解決などに向けた支援を行います。
また、サステナNetでは寄付という手段の他にもサービスを提供しており、複数の企業やNPOが連携して、特定の社会課題に向けてプロジェクトの設立・実行と可視化を目的とした「チャレンジマーケット」(外部リンク)も展開しています。
――おもしろい取り組みですね。これまでにどのような連携が生まれたのでしょう。
伏見:一例ですが、伝動・制御機器の総合メーカーである三木プーリ株式会社(外部リンク)は、工場がある山形県米沢市が抱える人口減少の課題を解決したい、お世話になってきた米沢市に“恩送り”をしたいという思いからわくわく寄付コンペに参加しました。
コンペの結果、連携することになったのがひきこもり当事者の就労支援を行う団体です。三木プーリは工場見学の機会をつくることで就労の可能性を広げたほか、継続的な寄付コンペを通じて、地方自治体等との地域ステークホルダーとの連携強化が行われています
私たちとしても新しい都市と地方との関係性が生まれたことがとてもうれしく思いましたし、地域と密接につながる企業の在り方として、NPOとの連携は大きな価値の一つだと感じた取り組みでもありました。
また、チャレンジマーケットに参加した株式会社オープンアップグループ(外部リンク)は、ICT人材のキャリア支援を行う企業なのですが、広島県を舞台にICTと自然体験をかけ合わせた「こどもテックキャラバン」(外部リンク)を実施しました。

伏見:このプロジェクトでは里山、里海の課題に取り組む2つの団体に、全国に結婚式場を展開する株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ(外部リンク)も加わり、最終日には結婚式場で発表会が行われるようになりました。
こんな風に、自社が培ってきた経験や強みを活かして社会貢献に参加できる企業はまだまだたくさんあると私たちは考えています。
――企業が社会貢献に取り組もうとするとき、社内で理解を得るのが難しいとか、上層部が反対して前に進まないケースがあると聞きます。
伏見:ええ、たくさんあります。そうした企業のトップの方々としては、昨今重要視されているサステナビリティの定義がとても広く、サステナビリティ経営、人的資本経営、社会貢献を整理し、全体の取り組みを把握された上での意思決定を行うことが、非常に困難な状態になっていると感じています。
こうした現状を踏まえ、2023年からは自社の取り組みがどのように社会への影響を生み出しているのかを可視化し、サステナビリティ経営を戦略的に行うためのレポートを作成する「サステナサマリー」(外部リンク)というサービスも始めています。
――サステナNet以外にも、いろいろなサービスを展開されているんですね。
伏見:私たちは「誰もが社会課題解決の主役になれる世界」をビジョンに掲げています。主役といっても、いわゆるヒーローのような存在を目指しているわけではなくて、社会課題解決のために企業、NPO、自治体、個人、それぞれにしかできない役割があると考えているんですね。また、個々にできることには限りがありますから、それぞれの役割を全うするために、さまざまな角度から「共助共創」の仕組みを作っています。

今後はますます、企業・NPO・自治体・個人の枠を超えた連携が重要に
――企業とNPOが互いを知り、理解を深めるために、まず何が必要なのでしょうか。
伏見:やはり、対話をする機会をつくることからでしょう。まずはお互いが解決したい課題をベースに、それぞれができること、できないことを共有し合う。
このとき、双方が活動する現場に足を運ぶことも重要です。こうした対話が信頼関係を構築し、本当に適切なパートナーとはどんな存在なのかを考えるきっかけにもなります。結果として連携が生まれなかったとしても、十分に意義があると思います。
――本当に「お見合い」と同じなんですね。今後はどのような展開を考えていますか。
伏見:このまま少子高齢化が進んで労働人口が減少すれば、自ずと課題解決に取り組む人口も減少していきます。そうなると、企業とNPOが連携することで生産性が高まる構造をつくらなければ、課題解決に向けて進めることは難しいでしょう。
課題解決を実現するためには、企業・NPO・自治体のセクターを超えた連携が必要になりますが、企業は売上げや利益重視、NPOは課題解決重視、自治体は生活者のインフラ整備など、同じ課題に対して、それぞれの主目的と視点が微妙にずれている実態を捉えて、連携をサポートすることが重要です。
今後は企業とNPOとの連携に加えて、同じ課題解決に向けて活動しているNPO同士の連携もサポートできたらと思っています。
また、将来的には、社会課題ごとにデータをまとめ、それぞれの課題がどの程度解決されているかを評価できる仕組みを作り、個人ユーザーがサステナNetに自分の地域の社会課題や情報を提供することで、NPOや企業の取り組みをサポートできるようにもしていきたいですね。

――最後に、社会課題解決のプレーヤーを増やすには、どうすればよいと思われますか。
伏見:まずは社会課題に対して認知を広げ、社会全体で「解決しなければいけない」と認識すること。実際に、サステナNetを活用している企業の方からは「こんな課題があったなんて知らなかった」という声をたくさんいただいています。
その上で、さまざまな課題に取り組む団体の存在をひと目で分かるような仕組みを作ること。さらにいえば、個人も企業も、個々の取り組みに対してお金を寄付すること以外にも、ボランティアやより簡単な日頃の生活を通じて、さまざまな形で参画できる選択肢が増えたらいいなと思います。
企業や自治体などが、社会貢献に一歩踏み出すためのきっかけや新しい選択肢をつくることが、プレーヤーを増やすことにもつながるのではないでしょうか。
編集後記
ICHI COMMONSが提供するサービスの共通点は、企業・NPOを問わず目の前にいる人に寄り添い、ニーズに耳を傾けること。サービスを活用した企業や団体は、時間をかけて信頼関係を築く中で、思いもかけないマッチングやユニークなアイデアが生まれてきたのではないでしょうか。
創業前に約1,200のNPOへ実態調査を行い、人事・広報・組織運営などさまざまな観点から現状や課題をヒアリングしたという伏見さんは、「まだまだできることがあるはず」と現在もチャレンジを続けています。
この姿勢こそが、社会課題を解決するための第一歩だと感じました。
撮影:永西永実
〈プロフィール〉
伏見崇宏(ふしみ・たかひろ)
慶應義塾大学法学部卒。学生時代に教育系NPOのHLAB立ち上げに携わる。2014年にGeneral Electric入社、FMPプログラムの一環でコーポレートファイナンスを中心としたプロジェクトに従事した後、インパクト投資の中間支援をする一般社団法人C4に事務局長として参画。同時期に米系ファンドEVOLUTION FINANCIAL GROUPの投資銀行部門にて、上場株式投資のアレンジャー業務に従事。2020年、ICHI COMMONS株式会社を創業。日本の社会課題解決の為に誰がどこで何に取り組んでいるのかを可視化するプラットフォーム「サステナNet」を通じて、企業のサステナ推進支援やNPO・社会的事業の課題解決促進に取り組む。
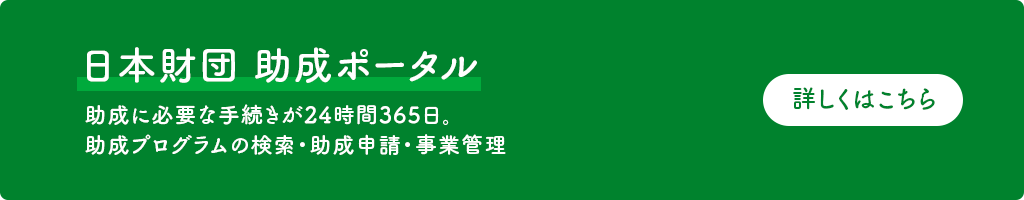
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。













