社会のために何ができる?が見つかるメディア
発達障害傾向、不登校——困りごとを抱えた子どもたちの居場所づくり。必要なのは「自己理解」を促す支援

- 困りごとを抱えた子どもたちには、発達障害傾向や孤独などさまざまな背景がある
- 一般社団法人ヒトノネは、困りごとを抱えた子どもたちにとって放課後の秘密基地のような場所
- 「自己理解」を深め、好きなことに夢中になれる居場所づくりが、子どもたちの可能性を引き出す
取材:日本財団ジャーナル編集部
新学年がスタートしました。クラス替えや新しい友だちとの出会いに胸を踊らせている子どもたちがいる一方で、緊張や不安を抱えている子どもたちも少なくありません。一度でも勉強でつまずいたり、集団生活にうまくなじんだりすることができなかった経験のある子どもたちは尚更でしょう。
そんな困りごとを抱えた子どもたちを支援しているのが、岐阜市にある一般社団法人ヒトノネ(外部リンク)です。「探究型学童保育ヒトノネ」「放課後等デイサービスみちな」「Imaru個別指導塾」「クリエイターズ・クラブ」の4つのサービスを展開し、発達障害傾向のある子どもも含めた、さまざまな子どもたちに、家でも学校でもないもう1つの「居場所」を提供しています。
なかでも特長的なのが、芸術や音楽といったクリエイティブ活動に力を入れているところ。防音室をはじめ、アートスペースや映像編集機器などを充実させ、子どもたちが「好きなこと」に情熱を注げるよう支援しています。

この記事では、そんなヒトノネの代表を務める篠田花子(しのだ・はなこ)さんに、困りごとを抱えた子どもたちの支援内容や、ヒトノネの活動に込めた思いについてお話を伺います。
「自分を理解すること」が、生きやすさにつながっていく
――ヒトノネに通う子どもたちは、学校生活の中でどのような困りごとを抱えがちなのでしょうか?
篠田さん(以下、敬称略):ヒトノネにいる子どもは定型発達(※)・グレーゾーン・発達障害傾向のある子どもと実にさまざまですが、例えば発達障害傾向のある子どもを例に挙げると学習障害の傾向がある子どもの場合、集団生活はできるし一見何も問題なさそうなんですが、黒板に書かれた字をノートに書き写すことが難しかったり、本を読むことが苦手だったりすることがあります。
学習障害の中には、例えば文字がグニャグニャに見えて、脳内でうまく処理できなかったりする子どももいるんですね。ただ、障害のことを知らない人からは、ただただ“できない子”としてレッテルを貼られがちです。親でさえ、その知識がなければ「どうしてできないの? 本人が怠けているだけでは?」と思ってしまうこともあります。
また「周囲の変化に過敏な子」もいます。集団登校する際、いつもと違う場所に集合することになったんですが、どこにどう並べばいいのか分からなくなって、パニックになり、突然泣き出してしまって……。普段と違う環境や状況に適応することが難しいんですね。
- ※ 「定型発達」は発達障害と対比する際に使われる言葉で、年齢に応じた身体的、知的、社会的、情緒的な発達が順調に進んでいる状態を指す
関連記事:怠け者と勘違いされることも。読み書きに困難のある学習障害「ディスレクシア」とは(別タブで開く)

篠田:しかも、これらの特性は一人一人、内容も程度も異なります。なので、どうしても周囲からは理解されづらいんです。本当は“定型”なんてなくて、誰しもがグレーで、グラデーションがあるのが人間だと思うんですけどね。
――なかにはここ数年で広く認知されるようになった特性もあるかと思いますが、それでもまだまだ理解は追いついていないのですね。
篠田:そうですね。だから、発達障害傾向にある子に限らず、まず困りごとを抱えた子どもたちには、自分で自分のことを理解する「自己理解」を促しています。自分には何ができて、何が難しいのか。得意なことの能力を発揮するためにはどんな環境があればいいのか。
そういったことを理解した上で、周囲にもちゃんと伝えられるようになること。それができるようになると、自然と周囲の人たちの理解も得られるようになるのではないか、と考えています。
――「自分のことを言語化する」というのは小さな子どもでもできるものなのでしょうか?
篠田:できるようになります。例えばヒトノネに通っている小学2年生の男の子は、人前で話すことが本当に苦手なんですが、事前に準備さえしておけば堂々と話せることが分かりました。
そこで、「先生にそのことをちゃんと伝えてごらん」と促してみたところ、自分の言葉で「ぼくは準備をしないとちゃんと話せないから、先に準備してもいいですか」と先生に言えたんです。それがきっかけとなり、別の授業のときにも先生へのヘルプを出しやすくなりました。
肝心なのは、「自分の困りごとを打ち明けても大丈夫なんだ」という安心感を得ること。その小さな成功体験が一歩となって、少しずつ周囲に自分のことを伝えられるようになっていくんです。ヒトノネではそれを大切にしています。
決して否定せず、さまざまな選択肢を示す
子どもたちが「自己理解・自己決定」することを大切にするヒトノネでは、一人一人のスタッフが子どもたちに寄り添うようにサポートしています。
ここで、実際にヒトノネで働く増村麻(ますむら・あさ)さん、矢島宗弥(やじま・そうや)さんに、子どもたちとの過ごし方や指導方法について伺いました。
――おふたりはどんな業務を担当されているのでしょうか?
増村さん(以下、敬称略):学童保育、放課後等デイサービス、個別指導塾、クリエイターズ・クラブの全てに携わっています。
子どもたちをサポートする中で私が大事にしているのは、「否定しないこと」です。誰にだって個性や特性がありますし、それを矯正するのではなく、うまく活かしながら生きていくことが、これからの時代には必要だと思うんです。ですから、どんな子であっても、その子のいいところを見つけて伝えるように意識しています。

矢島さん(以下、敬称略):私はクリエイターズ・クラブのスタッフとして、子どもたちに造形を教えています。ただ、人手が足りないときには他の業務も手伝いますし、個別指導塾では3人の子を担当しています。
その中では、「教える」ことだけを重視するのではなく、もう少し緩く「話し相手になる」ことを大切にしています。「先生と友だちの間にいる人」を目指しているんです。そんな交流を通して、人と関わることの経験を積んでもらえたらいいな、と思っています。

――ヒトノネに通い出してからの子どもたちの変化について、印象に残っているものはありますか?
矢島:以前、不登校状態にある小学6年生の子がいました。無理やり学校に通わせる必要はないと思いつつも、目標は持っていてほしくて……。すぐに決められなくてもいいから、将来の夢を見つけようと話していたんです。
すると、社会学に興味を持ち始めて、やがては自発的に「行ってみたい大学」のことも調べ出すようになりました。ここでの交流から、自分なりの目標を見つけてくれたことがとてもうれしかったですね。
増村:不登校の子には、まずはここが「安心できる場所」であることを理解してもらうように努めています。そうしているうちに、子どものほうから「やっぱり進学してみたい」と打ち明けてくれたりするんです。
また、私が意識しているのは、「選択肢を示すこと」です。例えば大学に行くことを迷っている子がいたら、「高校を卒業してすぐに働くのもいいし、大学に行きながら自分の将来を考えるという選択肢もあるんだよ」というように、できるだけ、いろんな道の中から選べる状況をつくってあげたい。いろんな選択肢があって、どの道がベストなのか、ちゃんと自分で考えて選んでもらいたいんです。
矢島:最初は無口な子も多いんですが、こちらから歩み寄るとだんだん話してくれるようになって、将来のことも相談してくれるようになる——私たちは親でも先生でもないからこそ、子どもたちも素直に話しやすいのかもしれません。
増村:それはあるかもしれません。個別指導塾で見ている子の中には、勉強が嫌いで仕方ない子もいます。お母さんに対しては「もうやりたくない、行きたくない!」と言ってしまう。でも、塾に来ると一生懸命に勉強するんです。つまり、勉強は嫌いなんだけど、やったほうが良いことは理解していて、それをうまく表現できずにいるだけなんですね。
ですから、私たちみたいな第三者が間に入ることで、子どもたちが前に進めることもある。それが、ヒトノネの存在価値だと思います。

ヒトノネに通う中で、自分の好きなものを深堀りできるようになった
ヒトノネに通う中で好きなこと、得意なことを見つけて、将来の道を見つける子どもたちは珍しくありません。
音楽ユニット「Hoshinone(ホシノネ)」(外部リンク)として活動する高校生のエツシさん、カノさんはヒトノネに通うまではごく普通の生徒でしたが、この場所で熱中できるものを見つけました。
――「Hoshinone」を結成することになったきっかけは?
エツシさん(以下、敬称略):ヒトノネでカノと出会って、一緒に音楽をやろうって誘ったんです。もともと曲作りをひとりでやっていたんですけど、僕は歌えなくて……。誰かいい人いないかな、と思っていたところ、カノと出会いました。

――そもそも、どうしてヒトノネに?
エツシ:学校では、音楽好きが集まるコミュニティにいたんですけど、人と揉めてしまって、居場所がなくなってしまったんです。そんなときに友人がヒトノネを紹介してくれて、通うようになりました。
カノさん(以下、敬称略):私は小学生の頃からヒトノネが運営する学童保育でお世話になっていました。中学生になって疎遠になってしまった時期もありましたが、DTM(※)講座が開かれていることを知って、また通ってみようかなと……。
- ※ 「Desk Top Music(デスクトップミュージック)」の略で、パソコンを使って音楽を作成・編集する作業の総称
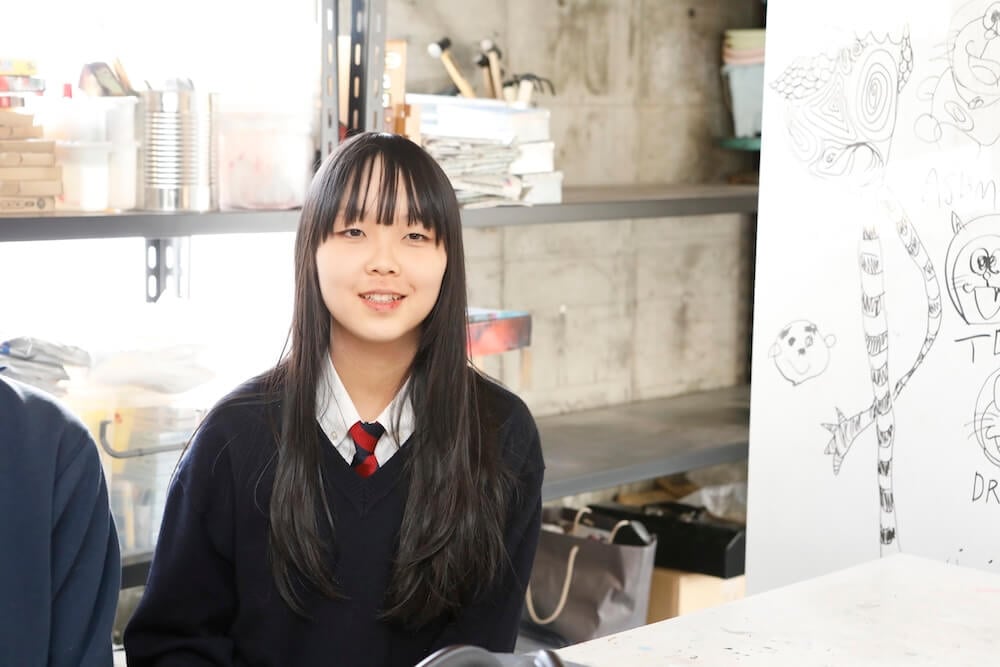
エツシ:ここで音楽に没頭するようになってから、表現の幅がどんどん広がっていったと思います。いろんな人と出会えるので、それまで興味が薄かった音楽ジャンルの話題も耳にするようになって、自然とあらゆる音楽を聞くようになったんです。結果的には音楽制作にも役立っているので、ありがたいですね。
カノ:私はヒトノネのおかげで、「自分の好きなもの」を深堀りできました。ここって好きなことに一生懸命な子が多くて、尖っていても認めてもらえるんです。だから、私も好きなことを追求していこうと、恐れることがなくなったように思います。
――おふたりの今後の目標も教えてください。
エツシ:4月から東京の音楽大学に通い始めるのでカノとは離れてしまうんですが、「Hoshinone」の活動にはもっと力を入れていきたいと思っています。大学で技術を磨いてパワーアップしつつ、良い曲を作って、カノに歌ってもらう。当面はそうやって楽曲制作をしていきます。
カノ:将来の夢はまだぼんやりしているんですけど、とにかく音楽をやっていきたいです。
困りごとを抱える子どもと社会とをつなげる役割を担いたい
「Hoshinone」のふたりのように、ヒトノネではクリエイティブな分野で力を発揮する人たちがいます。それはヒトノネがまさに、子どもたちのクリエイティブ活動を応援しているからです。ワークスペースには画材、工具、PC、楽器など、さまざまなものが揃っていて、興味に応じてチャレンジできる環境が整っています。
では、どうして「クリエイティブ」を意識するのか、改めて篠田さんに伺います。


――クリエイティブ活動ができる環境を整えた狙いはなんでしょうか。
篠田:岐阜の学校は運動部が盛んで、スポーツ好きな子たちは居場所をつくりやすいんです。一方、アートやモノ作りなどが好きな文化系の子たちにはなかなか居場所がない。ましてやDJや映像制作といったクリエイティブなことは学校内でできない領域も多い。それならば、ヒトノネの中にそういった場所をつくろうと思ったのが始まりでした。
クリエイティブ活動って、自分らしさを表現できるものだと思うんです。だから、この場所で思いっきり自分らしくいてもらいたい。それに、特に部活などに属していない中高生にとって、普段は周りから評価されないようなもの、だけど自分にとっては大切なこと・好きなことを表に出す機会が実は少ないんです。
本人は取るに足らないことだと思っていたり、恥ずかしくて人に見せられなかったものが、同じようにクリエイティブな属性同士なら分かり合えるものがある。ここに来れば、絵や音楽、プログラミングなど、できることをごちゃまぜにして横断的にいろんな人とも関われる。実はそこに将来の自立につながる何かが見つかることもあるんです。
「Hoshinone」のふたりもここで出会って、自発的に音楽ユニットを組みました。彼らの音楽を聞いたプロの方々も興味を持ってくれて、その人たちと一緒にミュージックビデオまで完成させました。その事実が、ふたりの活力にもなっていると感じます。
だからこれからも、クリエイティブに興味がある子たちのことはサポートしていきたいですね。
――日本財団の協力で完成した防音室はどのように活用されていますか。
篠田:ドラムセットを設置しているんですが、音楽好きな子はもちろん、そうじゃない子も叩いている姿を頻繁に目にします。ドラムって感情を発散するだけではなく、気持ちの調整能力にもつながるらしいんです。ですから、この防音室は、ひとりモヤモヤを抱えた子たちにとっての大切な場所になっています。
なかにはドラムを叩いているところを撮影してYouTuberになることを目指している子もいますし、周囲の音を遮断して録音している子もいますので、さまざまな面で役立っています。そういう子たちがまた才能を開花させていくかもしれませんね。

――ヒトノネはさまざまな可能性を発掘する場所になりつつありますが、今後の展望はありますか。
篠田:クリエイティブなことが好きな子どもたちの基地となること、そして、発達障害傾向やグレーゾーンの子どもたちへの理解をもっともっと広げていきたいと考えています。正直、支援の手は足りていないんです。だからこそ、学校や企業の人たちにも理解してもらいたいですね。
そのためにも、ヒトノネに通う子どもたちと企業の人たちの接点を増やしていこうと思っています。例えば、月に1度フードパーティーを開催しているんですが、企業の人たちにも声をかけて参加を呼びかけています。
そうして子どもたちと交流を深めていくことで、子どもたちが抱えている課題や発達障害・グレーゾーンとはどういうものなのか理解することにつながっていくと思います。結局はそれが社会全体のダイバーシティにもつながっていくと思うんです。

篠田:子どもたちは、やがて社会へと出て、自立しなければいけない。だとするならば、私たちはそのサポートをしたい。不登校の子たちには学校に行けるように、社会に出るのが不安な子たちには、その不安を払拭できるように。子どもたちが、その子なりに自立していくために、社会とつなぐ。それが、ヒトノネの役割なんだと思います。
編集後記
篠田さんが口にした「自己理解」という言葉に、ハッとしました。自分を理解することが生きやすさにつながり、また、将来の夢を見つける手立てにもなり得る。それを重視するからこそ、ヒトノネはたくさんの子どもたちの「居場所」になっているのだと感じました。
この場所で「自分らしさ」を見つけ出し、生き生きと輝く子どもたちが増えますように……。そんな想いでヒトノネの活動を見守り続けたい。そんなふうにと思える取材でした。
撮影:永西永実
〈プロフィール〉
篠田花子(しのだ・はなこ)
南山大学外国語学部卒業、東京学芸大学大学院教育学研究科(美術教育専攻)修了。広告制作会社にてディレクター、コピーライターとして勤めた後、子どもたちの放課後を豊かな時間にという思いから、2018年に一般社団法人ヒトノネを創立。3児の母。教育学修士・放課後児童支援員(認定)、公認心理師の資格を有する。
一般社団法人ヒトノネ 公式サイト(外部リンク)
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。













