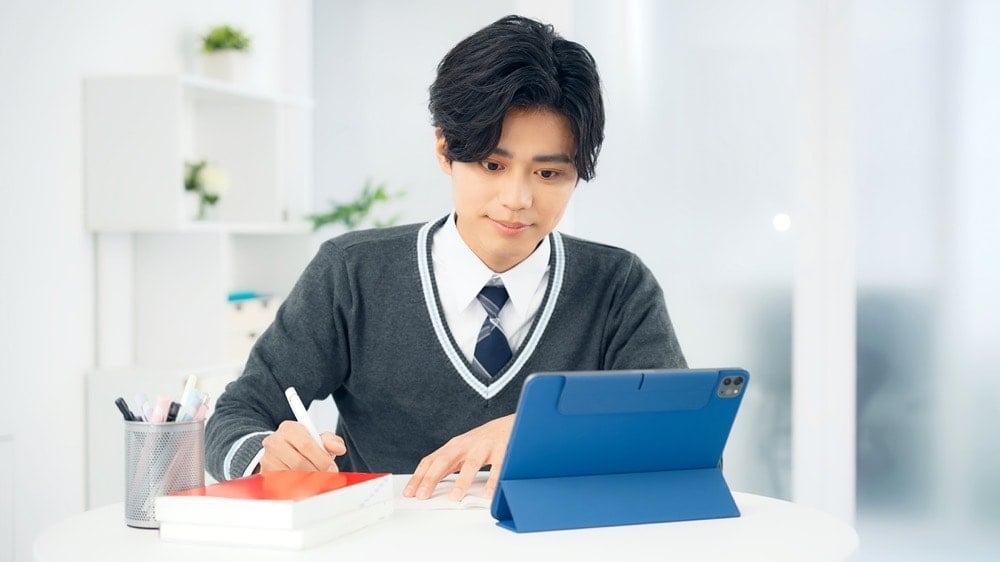未来のために何ができる?が見つかるメディア
寄付金を集める「ファンドレイザー」ってどんな仕事? 普段の業務を聞いた

- 「ファンドレイザー」はNPOの活動資源である寄付などを集める専門職
- 寄付を集める=単なる資金調達ではなく、「仲間を集める」ことだとの認識が必要
- ファンドレイザーの存在が、NPOの活動を広げ、社会を変える大きな役割に
取材:日本財団ジャーナル編集部
NPOをはじめとする非営利団体にとって重要な活動原資の一つである「寄付」。
団体の活動意義を伝え、個人や企業から寄付などを募る専門職「ファンドレイザー」には、経営や営業、広報などさまざまなスキルが求められるという。
今回、日本ファンドレイジング協会(外部リンク)の事務局次長・宮下真美(みやした・まみ)さんに、ファンドレイザーの実務や、求められる役割、必要なスキルなどについてお話を伺った。
NPOと一般市民をつなぐ、ファンドレイザーの存在
――そもそも「ファンドレイザー」とは、どんな職業でしょうか。
宮下さん(以下、敬称略):ファンドレイジングとは、「Fund(資金)」と「Raising(調達する)」を組み合わせた言葉です。文字通りNPOなど非営利団体の皆さんの活動に必要な寄付や助成金を獲得する職業であると同時に、寄付の裏側にあるさまざまな課題や、それを解決するための方法を一緒に発信し、仲間を集める人であると私たちは定義しています。

――日本ファンドレイジング協会では認定ファンドレイザー資格制度を設置し、研修など育成事業を行っています。具体的にはどんなことを学ぶのでしょうか。
宮下:オンデマンド研修やテキストを通して、ファンドレイザーの役割、定義、コミュニケーションなど基礎知識や、資金を得るための戦略・スキルなどを学び、身に付けます。
本来、資格がなくてもファンドレイザーとして活動することは可能ですが、「このまま自己流のやり方を続けていてもいいのか」jk、l。・「体系的にファンドレイジングを学びたい」という動機で受講される方が多いですね。
――ファンドレイザーになるためには、どのようなスキルが必要ですか。
宮下:私たちはファンドレイザーに求める役割として、以下の「5つの力」を定義しています。
- ファンドレイジングの知識とスキル
- ファンドレイジングの実行・実践力
- 誇りと倫理を守る姿勢・誠実さ
- マネジメント・コーディネーション力
- 対人コミュニケーション力
宮下:先ほどもお話したように、ファンドレイジングとは、単なる資金調達にとどまりません。
支援者や理事、ボランティアなど、組織の内外を問わずさまざまな方との関係を構築する上で、マネジメント・コーディネーション能力も求められますし、「寄付」という善意を預かる以上、誇りと倫理を守る姿勢も重要です。
資格試験の合格者には、世界的な国際基準を基に作成したファンドレイザーの行動基準に署名していただいた方を「認定ファンドレイザー」「准認定ファンドレイザー」の資格者として認定しています。
――日本にはどれくらいの数の認定・准認定ファンドレイザーがいるのでしょうか。
宮下:2025年4月1日現在、日本では約1,600名が認定・准認定ファンドレイザーとして活躍しています。
――ファンドレイザーは日頃、どんな企業や団体で、どのような業務をしているのでしょう。
宮下:私たちが資格者の皆さんに、ファンドレイジング業務に関するアンケート調査をしたところ、回答者の約半数は非営利組織に所属して活動していました。一方、組織に所属せず、外部支援者としてファンドレイジングに関わっている方もいます。
宮下:ひと言で組織といっても、NPOをはじめとする非営利組織や、一般企業で広報と兼任されていたり、経営企画部門として活動されていたり、本当にさまざまです。これは日本も海外も同じ状況ですね。
そのため、業務内容や働き方も人によって大きく異なります。例えば、街頭に立って寄付者を募る活動をされる方や、寄付者の方々に直接会いに行って寄付を募る方、オンラインでより多くの方々から寄付を集めるために広報的な活動をされている方などもいます。
また、経営の右腕的な存在として、寄付者の方々のデータを分析し、アプローチ戦略や事業戦略を策定する仕事をしている方もいます。
寄付を集めることは、「仲間を集める」こと。組織全体の理解が不可欠
――ファンドレイザーの仕事で、もっとも難しいことはなんでしょうか。
宮下:寄付を集めることや、支援者とのコミュニケーションと思われがちなのですが、実際は「組織の中での理解を広げること」がもっとも難しいポイントかもしれません。
というのは、さまざまな課題を抱えている人を支援したいという方の中には、「寄付としてお金をいただく」ことに対して抵抗感や嫌悪感を覚える方もいます。
また、行政から補助金や助成金を受けている団体では、寄付の意義や集め方が分からず、民間財源も必要だということがなかなか理解してもらえないケースもあります。
組織全体で、ファンドレイジングは“仲間を集める”ことだと理解した上で活動することが、寄付者、支援者を多く集める秘訣だと思います。

――だからこそ経営的な視点も必要なんですね。
宮下:もちろん、活動そのものに関心を持っていただき、「なぜこの活動にお金が必要か」を理解してもらうことも大切です。寄付者の方にとっては、あまり身近に感じられない課題だと、想像や共感がしづらいため、支援や寄付にはつながりにくいことがあります。
例えば、路上生活者など日本では自己責任論で語られることが多い問題は、多くの人にとって、自分ごととして捉えることが難しいでしょう。
それでも多くの支援者、寄付者を得ている団体は、自分たちの活動が単に目の前にいる人を救うだけではなく、「地域」「業界」「社会」の3階層に向けて発信しています。この活動や寄付が、どんな意義やインパクトをもたらすか、段階的に発信することでより多くの層の共感を集めているんです。
――思うように寄付が集まらないなど、苦労も多いように感じます。
宮下:確かに、寄付を募っても断られてしまうこともあります。でも、ちょっと意外かもしれませんが、多くのファンドレイザーには、寄付者から「寄付して良かった、ありがとう」と感謝された経験があるんです。こうした出会いや、お金の出し手、受け手の関係性を超え、社会の変化を促していく仲間としてコミュニケーションを取り合っている方々は、ファンドレイザーの仕事にやりがいを感じ、活動も広がっています。
NPOの活動が盛んになればなるほど、ファンドレイザーの存在が重要に
――ところで、宮下さんはなぜファンドレイザーになろうと思われたのでしょうか。
宮下:私は、前職はWEBマーケティングの仕事をしていました。やりがいを感じる一方で、さまざまな技術を駆使して、その人にとって本当に必要か分からないものを売りつけているような感覚があり、モヤモヤしていたんです。そんな時にファンドレイザーの存在を知り、興味を持ったのがきっかけです。
他にも、さまざまな職種、業界の方から転身されている方がたくさんいます。営業職から転身されたある方は、「前職で売っていた営業商材と違って、見えないものに対してお金を出していただく難しさはあるけれど、それ以上に心理的安全性が高い。社会にとって必要なことに自分の力を活かせることにやりがいを感じている」と話していました。
――内閣府によると、認証法人の累計は、2024年9月時点で約5万件(※)となっています。また、その中でも、寄付者が税制優遇を受けられる認定法人数は、年々増加しています。ファンドレイザーはさらに必要でしょうか。
宮下:ええ、必要です。私たちは、活動している全ての団体に、1人以上のファンドレイザーが関わることが理想だと考えています。
ファンドレイジングの専門家向けに、世界最大規模の資格認定制度を提供しているCFRE Internationalの2023年の調査(外部リンク/PDF)によると、アメリカでは8,000人を超える認定ファンドレイザーが活動しており、また、USニューズ&ワールド・レポート誌の「なりたい職業ランキング」(外部リンク)ではTOP30に必ず入るほど、専門職として認知されています。
日本にも「社会貢献活動には資金が必要であり、寄付にしかできない支援がある」という価値観を根付かせ、その大切な寄付を、倫理と信頼をもって託せる存在としての「ファンドレイザー」の認知を広げることで、これから志す人が増えていってほしいと願っています。
――ちなみに、知識や経験がない人や、営業活動やSNSでの発信が苦手な人も、これからファンドレイザーを目指すことは可能でしょうか。
宮下:可能です! ゼロから学ぶこともできますし、先ほどもお話したように、ファンドレイザーの役割は多岐にわたるので、「分析や戦略を立てるのは得意だけれど、対人コミュニケーションは苦手」とか、「SNSの運用は得意だけれど、WEBサイトの知識はあんまり……」ということもあるでしょう。
そんなときのために、私たちはファンドレイザー間のコミュニティ作りにも力を入れています。全ての業務を一人でこなす必要はなく、それぞれの専門分野や強味を活かし合っていくことがとても大切だと思います。
――ファンドレイザーや、NPOをバックアップするような人材は、どうすれば増えていくと思いますか。
宮下:多くの人にとっては、まだ「ファンドレイザーは何をしている人なの?」という存在です。一人一人のファンドレイザーが自分自身の活動を発信していくと同時に、私たちも認知を広げるためにさまざまな活動を続ける必要があるでしょう。
また、受け入れるNPO側も、正職員だけではなく、業務委託やプロボノ、ボランティアなど、ファンドレイザーの関わり方に多様性を設けることで、より多くの方の力を借りることができると思います。
――NPOの活動に関わりたい人を増やしたり、社会貢献活動に関心を持ってもらったりするためには何が必要だと思いますか。
宮下:NPOやその活動に触れる機会を増やすことが重要です。先ほどもお話したように、NPO側がプロボノやボランティア、学生の皆さんなど、多くの人に関わってもらう機会を増やすことも一つの手段です。
私はよく、母校で自分の仕事についてお話をする機会があるのですが、学生の皆さんはそこで初めて「ファンドレイザー」の存在を知るんですね。
こうした活動を通して職業の選択肢を広げてもらったり、NPOなどや社会貢献にかかわる仕事が職業として成り立つことを知ってもらったりすることが大切だと感じています。
編集後記
取材中、宮下さんが言っていた、「ファンドレイザーとは、社会を変えるプロフェッショナルだ」という言葉が印象に残っています。
ファンドレイザーの入り口となる「准認定ファンドレイザー」の資格は、18歳以上であれば未経験でも取得可能で、3年以上の有償実務経験も経た「認定ファンドレイザー」の中には、40代以上の方も多く活動されているとのこと。
こちらの記事で興味を持っていただければ幸いです。
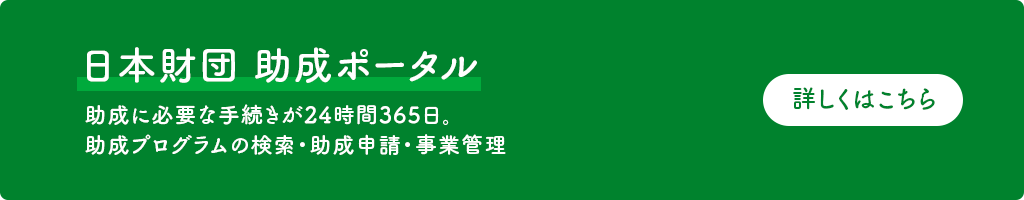
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。